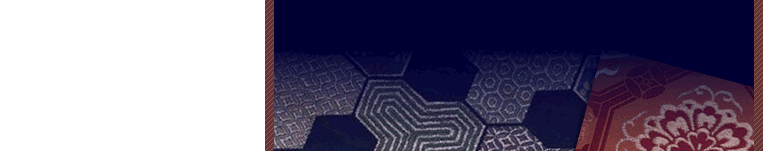私の城?です
|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
|
又新しいコーナー増えました。
歴史のコーナーです。 私はネットで歴史の事を調べる趣味が有るので、 その日その日にまつわる歴史話を少し掘り下げて、ブログのネタにしようという物。 私も歴史を調べた上に、まとめる事で考証する事が出来るという一石二鳥な企画です。 掘り下げると言っても、私が勝手に情報をつなぎ合わせる為に、一部妄想が入っていますが、話半分で読んで貰えると有り難いです。 さて今回ですが、よくある「今日は何の日」サイトによると、 「ヴァリニャーノ、長崎に遣欧使節を連れて帰り、印刷機を伝える(1590)」 と有ります。 そういう訳で、今日はこのヴァリニャーノさんについて調べてみましょう。 先ず、バリニャーノさんについて語る前に、 イエズス会について語らねばなりません。 イエズス会というのはよく歴史の教科書にも出て来ますが、 フランスの大学の学友6名が立ち上げた志を同じくする同士の集まりだった様です。青春の匂いがしますね。 6名はかなり真面目にキリスト教信仰を志していたらしく、青雲の志を持って一致団結したという所でしょうか。 勿論、教会関連のパトロン付きです。 ところで、この6名の中には、有名な「フランシスコ・ザビエル」さんが居ました。 このザビエルさんは日本に布教に来た事で有名ですが、日本局地的な有名人なのかと思ったら、日本以外にも色々な所に足を運んで布教活動を行った、世界的にも有名な人だった様です。 如何にイエズス会の布教活動が広範囲であったかが分かりますね。 イエズス会は信仰の一環としてかなり布教活動を重視していた様です。 では、ヴァリニャーノさんに話を戻しましょう。 彼はアレッサンドロ・ヴァリニャーノと言い、イタリア生まれ。 今で言うちょっとインテリな人で、コネも有ったので、教会関係で高く評価され、出世していた様。 そんな彼の大学の同級生に、たまたまイエズス会員が居た様です。 「今イエズス会ってのやってんだよ。イカスだろ!お前も一枚かまねえ?」 という感じでしょうか。 彼もイエズス会に入会します。 入会したヴァリニャーノさんは東インド方面の巡察師に抜擢されました。船に乗り旅立ちます。 数年掛けてインド付近各地を視察して回った後、日本へ向かう事になったのでした。 1597年。彼は日本にたどり着きます。 巡察師として織田信長と謁見の折、彼の連れていた黒人が大層信長の興味を惹きつけ、 その黒人は「弥助」と名付けられて、信長の直臣として取り立てられたそうです。 弥助はその後本能寺の変でも織田信長の傍に居たが、明智光秀に見逃されて助かったという記録が有ると無いとか、 どこかで読んだ様な記憶が有ります。はて、どこだったか。 話を続けましょう。 彼は日本人をかなり高く評価していた様です。 この後、かなり腰を下ろして本格的な布教活動に入る事になります。 先ず、司教教育の為の学校機関を日本に作り始め、 有名な「天正遣欧少年使節団」を企画します。 日本人をヨーロッパへ連れて行く事で、ヨーロッパに日本文化を、又、日本にヨーロッパ文化を紹介しようというのが、主な目的。 これによって布教活動もし易くなるという所でしょうか。 使節団はヨーロッパ各地で国王とか教皇とかに謁見した後、帰路に就きます。 その時に持って帰ったのが、 この長ったらしい話で一番重要だったはずの「活版印刷機」でした。 この活版印刷機は西洋では同年代の西洋では使われていない、相当古い型の物だった様です。 イイやつは持たせて貰えなかったのでしょうか。 それでも、ちゃんと実用には耐えて、実際に印刷された物が日本に残っている様です。 この印刷方式を「キリシタン版」と言うそうです。 日本に戻って来た彼らには困った問題が起きました。 日本の様相が少し変わっていたのです。 船で旅立っている内に、信長は明智光秀に殺され、今では豊臣秀吉が実権を握っていました。 信長はイケイケな新しい物好きでキリスト教を歓迎してくれたのですが、 どうやら秀吉は、イエズス会をヨーロッパの侵略行為の下準備と思い、警戒している様です。 「バテレン追放令」を出して、キリスト教を全面的に禁止してしまっていたのです。 これはややこしい事になりました。 使節団は行動にかなりの規制を付けられてしまいます。 幸いお咎め無しだったヴァリニャーノさんは日本を出る事になりました。 キリスト教の布教は以前と比べるとかなりやりづらい状況になっていました。 散々苦労して築き上げた布教活動を妨げた、この島国の主は、彼の目にどう映った事でしょうか。 その後も又、諸処の問題を片付ける為、日本に来たヴァリアーノさんですが、 最後の来日から日本を発って三年後、彼はマカオでその生涯を閉じたのでした。 さて、肝心のキリシタン版ですが、ローマ字表記の日本語でキリスト関連の書物が色々刷られたのですが、 結局日本文化は、印刷技術を別方式から取り入れ、このキリシタン版は日本に渡ったは良いが、その後の日本の印刷技術の発展の歴史には直接繋がらなかったとか。 となると、歴史的にはそれ程重要じゃないのか? 「結局どうでも良い話だったんかい」とかいう突込みは、「今日は何の日」のサイトにして下さい。 注意 この話はネットの資料及び、舞姫のうろ覚えの記憶と妄想で出来ています。 資料として使う際には十分に注意して下さい。 PR |
|
では、先ずはルールから語っていきます。
将棋にふれると自然に覚えていくと思うので、何となくでつかんでみて下さい。 将棋の基本ルール ○先手・後手、交互に駒を動かして行きます、自分の手盤(番)では駒を一度しか動かす事は出来ません。 ○それぞれの駒は動き方が違います(次回解説)。 ○自分の駒が動いた場所にいる相手の駒は取る事が出来ます。ただし、自分の駒がいる場所には動けません。 ○取った駒は持駒(もちごま)として手持ちにする事が出来、自分の手盤で駒を動かす代わりに、これを盤上に置く事も出来ます。但し、次にその駒が動けない位置には打てません。 ○自分の駒を相手の陣地、奥から三段目まで動かして入った時は駒を「成る」事が出来ます。又、すでに成れる場所にいる駒が動く時にも成る事が出来ます。 成った駒はひっくり返して使いますが、駒の動きが変わります。 勝利条件 ○最も分かりやすく言うと、相手の駒「玉」を先に取れば勝ちです。 但し、玉を取ってしまうのは悪いという事で、公式ルール上では相手玉を「詰ま」せれば勝ちという事になっています。 「詰み(つみ)」については後の回にくわしく解説しますが、言葉で分かりやすく言うと、 「次に相手の玉を取れる事が確実になった状態」です。 相手の玉に王手(※)が掛かっていて、相手の玉の逃げ場所が無い場合がそれにあたります。 その他ルールには、反則手として、 「打ち歩詰め(うちふづめ)」等が有りますが、詰みについて語る回に回します。 ここに書いてある物は、飲み込みやすい様に砕いた表現で語っている為、 将棋の公式ルールとは若干表現が異なります。 ある程度ルールをつかんだ後、正確なルールを確認したい時は、他サイトで確認して下さい。 ※王手 玉に敵方の駒が効いている状態。つまり次に敵方の駒が動ける場所に玉が居る状態。 |
|
初めに。
このブログでは特別編として、将棋の講座をやって行こうと思います。 でも将棋講座のサイトなんてどこにでも有る。 そういう訳で、このサイトの対象者は駒の動かし方も分からない「超初心者」です。 又、他のサイトでは取り上げられない部分等を重点的に扱って行こうと思います。 駒の動かし方を覚えてから実際にやってみるという実践への導入。 例えば、私は将棋は指しますが、チェスは出来ません。 でもチェス専門のサイトは多いので、ちょっと覗いてみたりするのですが、サイト内を見て、 それらしく解説されている物を観ても、直ぐにやってみようという風にはならないのですね。 「自分には難しそう」という意識が強いです。 多分多くのサイトは解説に留まって、実際に手取り足取り教えてくれるという部分が薄いので、 有る程度やってみて覚えた初心者には良いが、全然分からない超初心者の場合は、先ずやってみようという初動負荷を超えるのが難しいんだと思います。 そういう訳で、このブログでは丁寧にエスコートして行く予定。 このブログを見て疑問に思う事等有れば、超初心者の方は遠慮せずにコメント欄に書き込んで下さい。 |
|
いよいよ深刻になって来ました。
ネタ切れ問題。 これからどうしようかと考え中。 今回の記事は、漫画雑誌でよくある、作者休載につきの特別まとめ企画みたいな物です。 今後の展望についての事を考えてみます。 今企画している事。 ○別にオススメでも無い読んだ本の紹介。 (ある意味物凄く意義が薄いタダのネタ) ○将棋超初心者講座。 (これは物凄く回を稼げる) ○将棋自戦記。 (相当やりたくない、やるなら何かオリジナリティを) ○ニュース記事連発 (割と簡単だが、ブログの雰囲気が固くなりそう) ○不定期連載小説 (やらなきゃ良かったと途中で後悔しそう) ○将棋観戦感想 (自戦記よりは良さそう、でも指した人の許可が必要か) ○舞姫の電波話コーナー (これは自然に沸いて来るので連載は簡単。読者が付いて来れるか?) 何か紹介したりするのなら、やはりオススメ出来る物にしたいですよね。 別に勧めたい訳でも無い物のあら捜しをしてどこが駄目だとか批評家みたいな事言っても仕方ないし。 |

 カレンダー
カレンダー