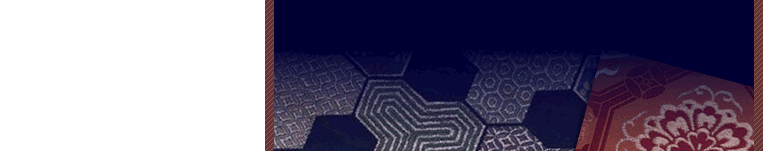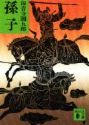
結構読者居る様なので真面目に書きます、
本のコーナー第三段。
「孫子」 海音寺 潮五郎
です。
歴史小説と言えば、
司馬遼太郎、吉川栄治位しか分からないのが私です。
歴史自体は好きなのですが、前に司馬遼太郎の小説、「燃えよ剣」を読んだ時に、どっと疲れてしまったので、以後、歴史物は敬遠して来ました。
「燃えよ剣」は新撰組の副長である土方歳三が主人公の物語です。
タイトルからしても、主人公がズバズバ斬りまくって血路を開いていくという分かり易い物語になりそうなのに、読んでみると、主人公の周りで繰り広げられる物語は文章中の三分の一有るかどうかで、
残りの文章は、当時の歴史的背景や、習慣の説明、著者の歴史学者的な見解で埋め尽くされているという物。その上、その説明は物語の途中で「そういえば」と著者が思い出したかの様に必要に応じて挿入されるので、まるで自動ヘルプナビゲーション機能をオフ出来ないWINDOWSソフトの如く、その疲れ加減は尋常では無かったです。
以来、歴史物は敬遠していたのですが、後で歴史小説好きの知り合いから聞く所によると、
歴史小説家にはそれぞれ作風が有り、特に司馬良太郎の作品は学者的な記述が多いので初心者向けでは無いとの事。
となると他の作者の物ならば、と思い手を伸ばしたのがこの「孫子」です。
孫子という著名な人物は歴史上には二人居るそうです。
中国の有名人達、老子、孟子、孔子等に見られる様に、「子」というのは尊称の様な物で、
孫子の場合は「孫」の一字が苗字となります。
二人の孫子はそれぞれ「孫武」(そんぶ)「孫臏」(そんびん)と言い、
孫武が初代孫子で、有名な「孫子の兵法」を書いたのもこの人。
孫臏の方は孫武の何世代か後の子孫であって、
どちらも兵法者として有名であったという事は変わり無い様です。
さて、今回読んだこの本はどちらが主人公だという話ですが、
両方が主人公でした。
内容は、前半が孫武編、後半が孫臏編と分けられており、両方の人物伝と、それぞれの時代背景等を楽しめます。
孫武編においては、冴えない戦略マニアのオッサンである孫武が、
中国史でも有名な大物の野心家武将、伍子胥(ごししょ)に見出され、「先生」として無理やり軍師に祭り上げられ、
最終的に中国の小国であった呉を大軍団に育て上げ、中国一の強国であった楚を破った後、戦に嫌気が指して引退するまでの話が語られており、
孫臏編においては、有名軍師である孫武の孫として生まれた孫臏が、共に兵法について学んだ親友の龐涓(ほうけん)に裏切られた為に、膝切りの刑にあって両足を失い、
復讐の為に龐涓の敵国に取り入り軍師となって、龐涓が率いる軍を策略合戦で打ち破って復讐を果たすという話の流れ。
結局読み物としては、中国史そのものが面白いと思われて、ストーリー自体楽しんで読める物でした。
作者の海音寺潮五郎さんという人は、1901年生まれという明治生まれの作家さんで、歴史小説の元祖みたいな存在の大家であるそう。
明治生まれだから司馬遼太郎の10倍読みにくくて難しい内容になりそうな物なのに、語り口調が学者的では無く、昔話でも語る様に分かり易い文章なので、10倍読み易かったです。
日本の卑弥呼の時代は中国史では三国志の時代。
孫子の時代は三国志よりも未だ前の時代で、歴史的資料も少ない筈なので、
面白おかしく書かれている小説のどこからどこまでが史実なのかは分かりませんが、
やはり歴史小説初心者の私にはこれ位の小説が良い様です。
又歴史小説を読んでみようという気にさせてくれたという意味で、個人的には読んで良かった小説と思います。

 カレンダー
カレンダー